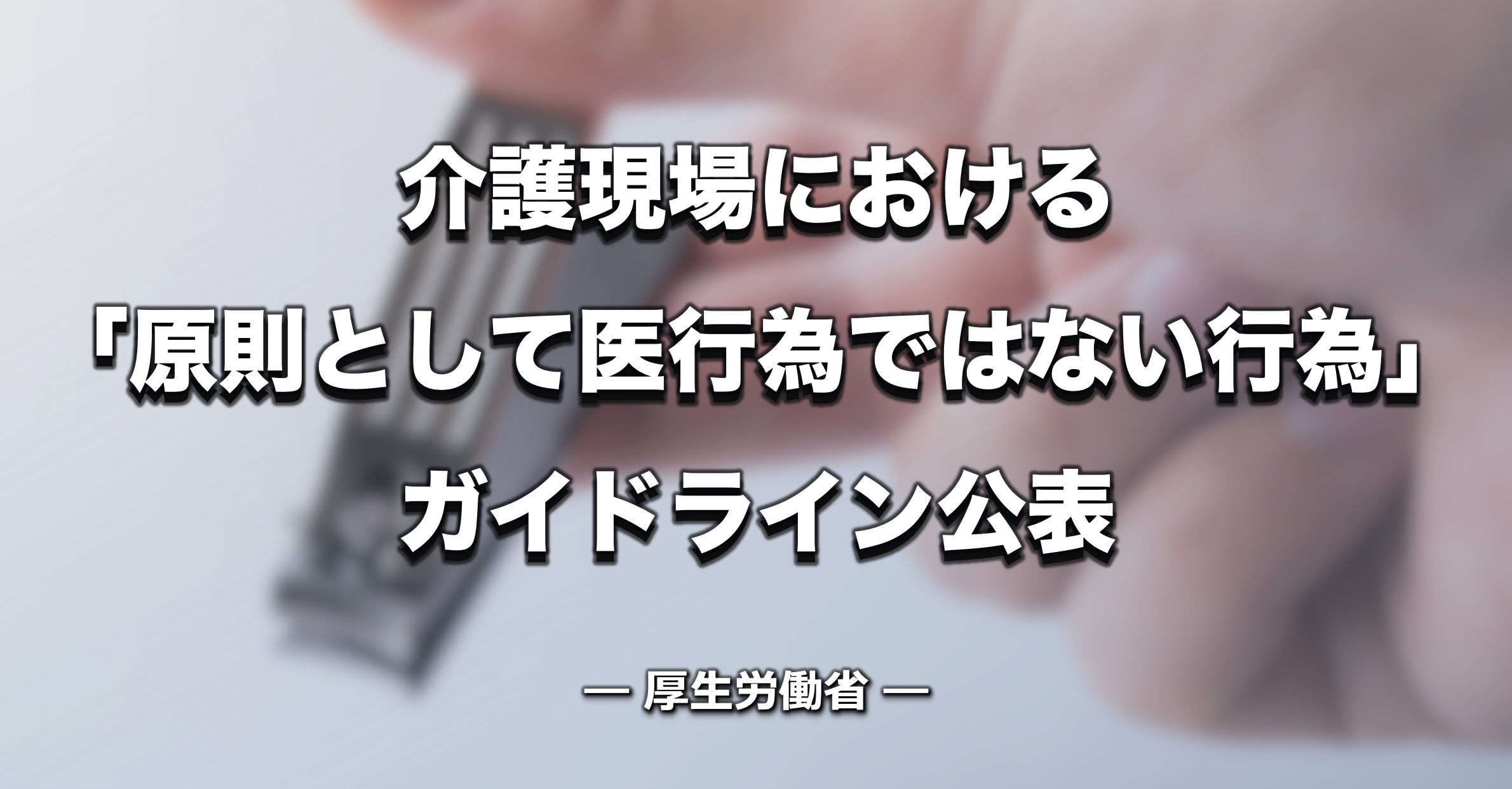理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
PT-OT-ST.NET
トピックス
2025.06.20
【厚労省】介護現場における「医行為ではない行為」ガイドライン公表
厚生労働省は5月、介護現場における「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインを新たに公表した。
本ガイドラインは、過去の厚生労働省通知(平成17年及び令和4年の医政局長通知など)で示された行為を基に、有識者による検討会や実際の介護現場へのヒアリング調査を通じて作成された。
これまで、医療行為ではないとされながらも介護現場で判断に迷う行為については、厚生労働省の通知などで解釈が示されていたが、実際の介護現場では「判断に迷う状況が生じている」との声もあり、周知が不十分であるとの指摘があった。
また、利用者の生活の質を維持・向上させるために必要な支援行為であっても、「医行為」に該当するかどうかの判断が曖昧なケースが多く、現場の職員が萎縮してしまう場面も少なくなかった。
その点、本ガイドラインは、セラピストや介護職員が現場で判断に迷いがちな行為について、安全性や適切性の確認ができるよう情報が整理されており、現場で当該行為を実施する上で参考となる。
「医行為ではない行為」の一覧では、食事や排泄、移動に関する支援に加え、バイタルサインの測定や福祉用具の操作など、日常的に行われている行為も含まれており、それぞれに注意すべき条件や留意点が記されている。また、介護職員が安心して実施できるよう、「医行為ではない」とされる根拠や実施時の配慮事項も補足されている。
現場の判断を支える実践的な資料として、多職種連携や医療との連携体制の整備にも資する内容となっており、今後は、各介護事業所がこのガイドラインを参考に、マニュアル整備や職員研修が推進されることが期待される。
「原則として医行為ではない行為」一覧
※留意点
「原則として医行為ではない行為」には実施する上で、通知上の条件が付されている。
以下の行為は「原則として医行為ではない」とされているが、利用者の状態や実施環境によっては医行為とみなされる場合がある。実施にあたって、事業所内のマニュアルや医療職との確認を行う必要がある。
「原則として医行為ではない行為」には実施する上で、通知上の条件が付されている。
以下の行為は「原則として医行為ではない」とされているが、利用者の状態や実施環境によっては医行為とみなされる場合がある。実施にあたって、事業所内のマニュアルや医療職との確認を行う必要がある。
バイタル測定
◯ 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること◯ 自動血圧測定器により血圧を測定すること
◯ 半自動血圧測定器(ポンプ式を含む。)を用いて血圧を測定すること
◯ 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
◯ 新生児以外の者であって入院治療の必要ないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメーターを装着し、動脈血酸素飽和度を確認すること
血糖測定関係
◯ 利用者への持続血糖測定器のセンサーの貼付や当該測定器の測定値の読み取りといった、血糖値の確認を行うこと在宅介護等の介護現におけるインスリンの投与の準備・片付け関係
◯ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、あらかじめ医師から指示されたタイミングでの実施の声かけ、見守り、未使用の注射器等の利用者への手渡し、使い終わった注射器の片付け(注射器の針を抜き、処分する行為を除く。)及び記録を行うこと◯ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、利用者が血糖測定及び血糖値の確認を行った後に、介護職員が、当該血糖値があらかじめ医師から指示されたインスリン注射を実施する血糖値の範囲と合致しているかを確認すること
◯ 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、利用者が準備したインスリン注射器の目盛りが、あらかじめ医師から指示されたインスリンの単位数と合っているかを読み取ること
経管栄養関係
◯ 皮膚に発赤等がなく、身体へのテープの貼付に当たって専門的な管理を必要としない利用者について、既に利用者の身体に留置されている経鼻胃管栄養チューブを留めているテープが外れた場合や、汚染した場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと◯ 経管栄養の準備(栄養等を注入する行為を除く。)及び片付け(栄養等の注入を停止する行為を除く。)を行うこと。なお、以下の3点については医師又は看護職員が行うこと。
①鼻からの経管栄養の場合に、既に留置されている栄養チューブが胃に挿入されているかを確認すること。
②胃ろう・腸ろうによる経管栄養の場合に、び爛や肉芽など胃ろう・腸ろうの状態に問題がないことを確認すること。
③胃・腸の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量から胃や腸の状態を確認し、注入内容と量を予定通りとするかどうかを判断すること
食事介助関係
◯ 食事(とろみ食を含む。)の介助を行うこと喀痰吸引関係
◯ 吸引器に溜まった汚水の廃棄や吸引器に入れる水の補充、吸引チューブ内を洗浄する目的で使用する水の補充を行うこと在宅酸素療法関係
◯ 在宅酸素療法を実施しており、利用者が援助を必要としている場合であって、利用者が酸素マスクや経鼻カニューレを装着していない状況下における、あらかじめ医師から指示された酸素流量の設定、酸素を流入していない状況下における、酸素マスクや経鼻カニューレの装着等の準備や、酸素離脱後の片付けを行うこと。ただし、酸素吸入の開始(流入が開始している酸素マスクや経鼻カニューレの装着を含む。)や停止(吸入中の酸素マスクや経鼻カニューレの除去を含む。)は医師、看護職員又は利用者本人が行うこと◯ 在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素供給装置の加湿瓶の蒸留水を交換する、機器の拭き取りを行う等の機械の使用に係る環境の整備を行うこと
◯ 在宅人工呼吸器を使用している利用者の体位変換を行う場合に、医師又は看護職員の立会いの下で、人工呼吸器の位置の変更を行うこと
在宅酸素療法関係
◯ 在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素流入中の酸素マスクや経鼻カニューレがずれ、次のいずれかに該当する利用者が一時的に酸素から離脱(流入量の減少を含む。)したことが見込まれる場合に、当該酸素マスクや経鼻カニューレを元の位置に戻すこと・肢体不自由等により、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困難である利用者
・睡眠中や意識がない状態で、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困難である利用者
膀胱留置カテーテル関係
◯ 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックからの尿廃棄(DIBキャップの開閉を含む。)を行うこと◯ 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックの尿量及び尿の色の確認を行うこと
◯ 膀胱留置カテーテル等に接続されているチューブを留めているテープが外れた場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと
◯ 専門的管理が必要無いことを医師又は看護職員が確認した場合のみ、膀胱留置カテーテルを挿入している利用者の陰部洗浄を行うこと
排泄関係
◯ ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)◯ 専門的な管理が必要とされない、肌への接着面に皮膚保護機能を有する肌に密着したストーマ装具を交換すること。
*「ストーマ装具」には、面板にストーマ袋をはめ込んで使用するもの(いわゆるツーピースタイプ)と、ストーマ袋と面板が一体になっているもの(いわゆるワンピースタイプ)の双方を含むものである
◯ 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
◯市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること
※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの
その他関係
◯ 有床義歯(入れ歯)の着脱及び洗浄を行うこと◯ 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
◯ 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
◯ 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
◯ 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
※切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急処置を行うことを否定するものではない。
服薬介助関係
◯ 皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)を介助すること◯ 皮膚への湿布の貼付を介助すること
◯ 点眼薬の点眼を介助すること
◯ 一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)を介助すること
◯ 肛門からの坐薬挿入を介助すること
◯ 鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること
◯ 水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は外用液の塗布(褥瘡の処置を除く。)を介助すること
◯ 吸入薬の吸入を介助すること
◯ 分包された液剤を介助すること
引用・参考
■ 介護保険最新情報 Vol.1385 「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて(厚生労働省HP)
■ 原則として医行為ではない行為に関するガイドライン(株式会社日本経済研究所HP)
■ 令和6年度老人保健健康増進等事業 介護現場における医行為ではない行為に関する調査研究(株式会社日本経済研究所HP)
この記事が気に入ったらいいね!しよう
人気記事
- 【速報】令和8年度診療報酬改定 個別改定項目(その1)
- 【公開】令和8年度 診療報酬改定 特設サイト
- 【介護報酬改定】訪問リハビリも処遇改善加算の対象に、PT・OT・STの給与改善へ ー 令和8年度・期中改定
- 【衆議院選挙】リハビリテーション専門職の候補者、各地で立候補
- 【座談会レポート】自分の能力を最大化させる、セラピストのリアルなAI活用
- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む
- 【診療報酬改定】早期リハの評価・休日リハ・単位上限・書類業務の削減などが論点に【中医協・総会】
- 【リハ関連抜粋】2026年度診療報酬改定 入院・外来医療等の「中間とりまとめ」了承 ー 中医協
- 【リハ関連抜粋】令和8年度診療報酬改定の議論を整理 ー 中医協
- ケアプラン連携システム「1年間無料+助成金」で支援 ー 厚労省が導入を後押し
- 【速報】令和8年度診療報酬改定 個別改定項目(その1)
- 【公開】令和8年度 診療報酬改定 特設サイト
- 【介護報酬改定】訪問リハビリも処遇改善加算の対象に、PT・OT・STの給与改善へ ー 令和8年度・期中改定
- 【衆議院選挙】リハビリテーション専門職の候補者、各地で立候補
- 【座談会レポート】自分の能力を最大化させる、セラピストのリアルなAI活用
- 【論点まとめ】リハビリテーションの評価はどう変わる? 令和8年度診療報酬改定を読む
- 【診療報酬改定】早期リハの評価・休日リハ・単位上限・書類業務の削減などが論点に【中医協・総会】
- 【リハ関連抜粋】2026年度診療報酬改定 入院・外来医療等の「中間とりまとめ」了承 ー 中医協
- 【リハ関連抜粋】令和8年度診療報酬改定の議論を整理 ー 中医協
- ケアプラン連携システム「1年間無料+助成金」で支援 ー 厚労省が導入を後押し
- もっと見る 省略する
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。
この記事を見た人はこんな記事も見ています
あなたは医療関係者ですか?
ページ上部へ戻る