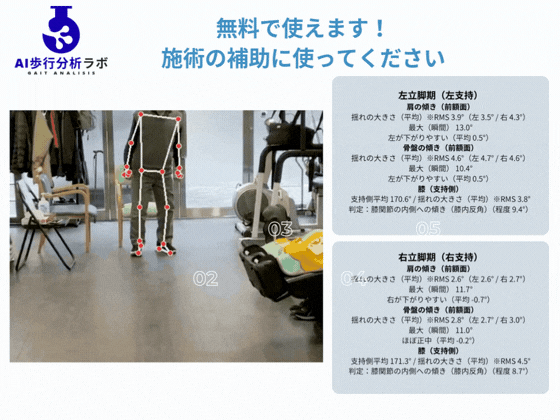理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
PT-OT-ST.NET
PT-OT-ST.NET掲示板
閲覧数:11185 2025年04月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
- 2025.04.21 21:48
-
10:たね更新日:2025年04月28日 23時18分
少し言葉足らずだったと思いますので追記します。
メカニズムは同じでも、より効率的な方法はあります。
先程の例えではトレーニングマシーンを使うことでより効率的に能力向上が出来ます。
運動麻痺ですと世界のガイドラインでは電気療法はマストです。
しかし、これは電気療法が優れてるのではなく、電気療法により重度の人でも反復出来ることがポイントです。
同様に日本での脳卒中でエビデンスのある手技は川平法がありますが、これも結局は反復がポイントなわけです。
これは基礎医学の生理学、運動学、解剖学に基づいているわけです。
ここに古典的な手技の弱点があります。
リハビリテーションの歴史で考えれば、今だに不明点は多くありますが、脳のメカニズムがわからない中で出来たものですから不出来なのは当然なわけです。
生理学、運動学、解剖学をしっかりと修めていればパラダイムシフトが起きても柔軟について行けます。
まずは、ひなまつさんが触れてますが、ガイドラインを読んでください。
素人が一人で簡単に出来る単純な自習トレであっても、疾患、国(個人的には日本、EBRSR、AAOS)別のガイドラインに沿った治療が提供できれば、必ず効果が出せます。
次に何でそれが効果が出るのかを生理学、運動学、解剖学の観点から説明できるようになってください。
方法は元となる文献を読むことです。
それだけで日本のトップクラスのセラピストになれますよ。 -
9:ペテセラピスト更新日:2025年04月28日 16時32分
確かに手技のエビデンスは高くないとは思います。しかし、軽度の麻痺に対して患者がそれれも治したい希望がある時にPNFを持っていたらななど思うときはあります。もちろん、それが絶対とは言えません。しかしそれに頼るのではなく、武器として持っておくことは良いとは思います。
手技を学ぶことは研鑽使用すると気持ちがあるということですから、いろいろ学んでみたり、手技をやっている方の考え方を聞いたりして、自分なりの答えを見つけることが良いことかと思います。
患者のゴールを考え、行動すること。手技に走り患者のゴールを見失う、誰にでも同じリハをするようなことがなれけばそれで良いのだと思います。 -
8:pos1235更新日:2025年04月27日 23時20分
手技に憧れてしまうのは、自分の無知から逃げたかったからと感じました。
ガイドラインも勉強し直します。 -
7:ひなまつ更新日:2025年04月27日 22時27分
私は手技についてはそれほど興味ありませんし、固執した介入はしていません
理由はガイドラインのエビデンスレベルがそんなに高くないからです
周りにはマジックハンドみたいなリハビリして患者さんのQOLあげてるセラピストもいるにはいますが、
どんな手段であっても患者さんが満足するなら否定するつもりもないので、手技好きな人は学べばいいと思ってます -
6:pos1235更新日:2025年04月26日 23時00分
すごくわかりますって言うと上からな感じがしてしまうのですが,とても納得するものが自分の中でありました。
自分が理屈や手技の理論が知りたいと思っていたのだと知ることができました。
自分の勉強不足はもちろんですが、どこでそんな知を知ったの?みたいなことがよくあり,それを知るためにも手技を習ってみたいと思います。
まずは、基礎コースよりかは、疾患や項目ごとなハンドリング研修などがあったので、受けてこようと申し込みました!
ありがとうございます。 -
5:emilio更新日:2025年04月23日 13時15分
「手技」というものにあまり固執しすぎるのもよくないです。
私も色々な手技を学びに行きましたが、皆様がおっしゃる通り、あくまで手段でしかないのですよね。
特定の手技で目の前の患者さんが良くなるわけではなく、科学的、解剖学的・運動学的・運動生理学的・病理学的に今このタイミングでこの運動をするから改善する…という根本がわかっていなければ、どんな手技を学ぼうが、患者さんは一生よくなりません。
様々な徒手療法・運動療法が考案されていますが、アプローチの仕方が異なるだけで、最終的に求めている結果は同じだったりします。
それが、筋緊張をコントロールするところから始まるのか、爆発的な力を起こして神経学的なところから始まるのか、関節の調整をしてアライメントを整えるところから始まるのか、ただそれだけの違いであって、結果は「患者の姿勢と動作が改善し、ADLないしQOLが上がること」以外の何物でもないです。
私の中で手技を習うことの位置づけは「自分の身体の使い方を学ぶ場所」「患者の本来の回復過程を療法士の触り方で邪魔しない(異常にしない)ための方法を学ぶ場所」と捉えています。(個人的な意見なので異論は認めます。)
身体の使い方の引き出しを多数持っている方が、自分が患者に直接触れて何かをしようとするとき、「理屈はわかってるのになんかうまくいかないな…」という時の潰しが利くことは間違いありません。そういった意味で、様々な手技を勉強しておくことは武器になるでしょう。
ですが、それはあくまで自身で勉強することであり、職場の同僚に求めることではないです。たね様がおっしゃる通り、究極を言えば、手技を勉強していなくても、理屈と原因がわかっていれば、患者を改善することは可能であるため、手技にこだわる必要はないです。
一般的なROMexや筋力トレーニング、動作練習を行っていたとしても、それが効果的な訓練であれば、療法士がベタベタ触らなくても良くなるものは良くなりますからね。結局のところ「患者自身が自分で身体を動かす」ことをしない限り、良くならないんです。療法士(自分)が触ったから良くなったんだ!と考えるのはあまりに烏滸がましい。確かに、手技によってその瞬間良くすることはできるかもしれないけど、その効果が何もせず継続することはありません。「患者が自分自身の身体をどう動かせばよいか」それを導いてあげるのが、私たち療法士の本分であり、「そもそも自分の身体の使い方がわかってなければ、患者に教えようがないでしょ…」これが手技を学ぶ本来の意義なのではないでしょうか。 -
4:Mokona更新日:2025年04月23日 07時16分
徒手療法や運動療法とはいっても様々な治療手段があり、ボバースやPNF,入谷式足底板といったものもありますね。
大事なのはこういった治療手段ではなく、その治療手段が身体にどういった変化を与えるのか?といった理屈です。
歩行時に膝が痛いといっても、病態によって介入手段は大きく変わります。単純なメカニカルストレスで痛いのであれば動作の改善、半月板の断裂による疼痛でアレば半月板の治癒必、末梢神経の阻血感作による影響であればこの環境の改善、骨の変形により軟骨下骨が刺激を受けているのであればこれの改善etc..
動作も中枢由来の動作障害なのかボディイメージの問題なのか、末梢由来の位置覚障害、エラー動作を学習しているetc..
動作異常・疼痛問わず、どのような病態で症状を呈しているのかによって介入手段は変わります。
なので、大切なのは手技ではなく理屈です。なぜ症状が出現しているのかという解剖-生理(病理)を理解することが一番重要です。そういった中でこんな病態や原因が経験上多いなーと感じたらそれに則した治療手段で介入を行います。
勉強会や講習は闇雲に受けるのではなく臨床経験上多く経験する病態に則した勉強会を受けたり、文献を引く事が必要だと思います。
上記の理由から私は手技には拘らず何故症状を呈しているのか、という理屈を深く学ぶことが必要だと思います。手技はあくまで手札の数です。手札は多いにこしたことはありませんが限られた手札を如何に使うか、というのもまた重要です。
なので手技に関しては臨床経験上、この手技や理論なら症状を改善できそうだな〜と感じられる臨床における悩みを解決できるものを受けることが望ましいと思います。 -
3:たね更新日:2025年04月23日 05時50分
正直に申し上げますと、手技に頼ってる時点で、あなたは勉強不足の出来ないPTだなとわかります。
医療は科学であり、科学はメカニズムが同じであれば結果は同じです。
最新の高価なトレーニングマシーンを使おうとも、自重であろうとも、部位にかかる総負荷量等々の条件が同じならば結果は同じです。
そして、運動は効果は確実ですがnon earlyですので地道な反復が必須です。
これらは生理学の極々一分の知識です。
今の職場の方々のほうが余程に積極的に学ぶべき場所だと思います。 -
2:あんらっきー更新日:2025年04月22日 09時32分
若いころに、ボ〇ース法、PN〇、関節〇ビライゼーションなどなどと、20年以上前に各種の手技に溺れていた、現在引退寸前の療法士です。
リハビリテーションという考え方には、手技は必要ありませんが、手技を用いて悦明をしながら行うと相手の選択枝と満足度は上がるのは間違いありません。療法士側にも、自分の選択した訓練方法への自信の後押しになるもの間違いありません。
ただ、患者さんのほとんどは、手技に対して満足度を得るのではなく、その療法士の患者さん自身の将来をいかに考えて細やかな対応をしているのかに満足を感じます。
私の臨床を通した結論ですが、手技は沢山の方法を学んだ方が良いと思います。実際の訓練は目の前のケースごとに考えて様々な手技を組み込み、単一の手技だけでそのケースの訓練を行わない。です。賛否あると思いますが、実際の臨床では、この手技がバッチリハマったという事はめったにありません。各種手技とオーソドックスと言われる生活での動作練習の組み合わせで、日々の臨床を行う事が一番多いです。
pos1235さんの人生の選択で職場の人に聞き続けてモヤモヤしてしまう方向で考えるのではなく、自ら手技を学んで実践する事をおススメします。何年かかかるかもしれませんし、もっと良くなっていたかもしれないと思う頻度は減らないかもしれませんが、自分に提供できる事はやったという感覚は増すと思います。 -
1:にゃうー更新日:2025年04月22日 08時48分
手技はあくまでもただの手段なので、手技ができる=治る、ではありません。
考え方を広げる、という意味ではさまざまな勉強会などに出向くのは良いことだと思います。
ただそれは職場に求めることではなく、自身で行動することです。
投稿者様は手技がやりたいのですか?リハビリをやりたいのですか?その先に何を見ているのでしょうか?
更新通知を設定しました
投稿タイトル:リハビリ手技について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:リハビリ手技について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
- コメント待ち2026.02.25
- 自立支援医療制度を利用して訪問リハビリを行う際の指示書のリハビリの記載内容について
- コメント待ち2026.02.24
- 個別サービス計画書について
- コメント待ち2026.02.24
- 感染症予防及びまん延防止のための対策について
- コメント待ち2026.02.18
- 回復期リハビリテーション入院料3
- コメント待ち2026.02.18
- 手術などの場合の早期リハビリテーション加算について
- コメント待ち2026.02.16
- 回復期病棟の早出、遅出のリハビリ単位について
- コメント待ち2026.02.12
- リハビリテーションデータ提出加算について
- コメント待ち2026.02.04
- 老健入所における加算の算定要件について
- コメント待ち2026.01.22
- 一体的サービス提供加算での口腔機能向上サービスのLIFE入力について
- コメント待ち2026.01.20
- 医療 訪問リハビリ期限について
- コメント待ち2026.01.15
- 精神での訪問リハビリについて
- コメント待ち2026.01.14
- 音声障害の算定について
- コメント待ち2026.01.13
- 訪問、通所、疾患別リハのリハビリ指示書の様式統一について
- コメント待ち2026.01.02
- クーリーフ治療の評価項目について
- コメント待ち2025.12.30
- 地域包括ケア病棟のリハビリ中止について
- コメント待ち2025.12.24
- 側湾症を学ぶために有効な参考書
- コメント待ち2025.12.23
- 電子カルテの生成AIについて(SSI)
- コメント待ち2025.12.22
- LIFEの実地指導開始について
- コメント待ち2025.12.04
- 地域包括ケア病棟のリハビリ1日2単位以上に、心リハ「集団療法」も含めてよいか?
- コメント待ち2025.11.21
- 【相談】発達ピラミッドの活用方法と手指の発達段階について教えてください
新着コメント
- 新着コメント2026.02.25
- リハの値段
- 新着コメント2026.02.25
- リハビリ以外の業務が20分につき1単位に含まれるのか?
- 新着コメント2026.02.25
- 副業について
- 新着コメント2026.02.25
- 休日リハビリテーション加算の算定方法について
- 新着コメント2026.02.25
- 「P84 専門性を生かした指導などのさらなる推進」の解釈について
- 新着コメント2026.02.25
- 興味関心チェックシート
- 新着コメント2026.02.24
- 回復期での実施計画書について
- 新着コメント2026.02.24
- 国の補正予算による賃上げについて
- 新着コメント2026.02.24
- 短期集中リハビリテーション加算と認知症短期集中リハビリテーション加算同時算定は可能?
- 新着コメント2026.02.22
- ペースメーカーの患者様の肩の痛み
- 新着コメント2026.02.20
- みなし単位
- 新着コメント2026.02.20
- 令和8年度診療報酬改定における、疾患別リハの新設項目「注7(離床を伴わない場合の減算および単位制限)」の解釈について
- 新着コメント2026.02.19
- 回復期リハビリテーション病棟変更内容
- 新着コメント2026.02.19
- 予防訪問リハビリ減算とマネジメント加算について
- 新着コメント2026.02.19
- セラピストのアクセサリー類の着用について
- 新着コメント2026.02.18
- FIM評価期間について
- 新着コメント2026.02.18
- リハビリテーション総合実施計画評価料算定要件について
- 新着コメント2026.02.18
- 休日リハビリテーション加算について
- 新着コメント2026.02.16
- 訪問リハ自費について
- 新着コメント2026.02.15
- 身体拘束、高齢者虐待防止の研修について
- 新着コメント2026.02.15
- リハビリテーション料
- 新着コメント2026.02.14
- マネージメント加算の会議について
- 新着コメント2026.02.14
- PTさんを目指し進路に悩む学生です
- 新着コメント2026.02.12
- 職場の雰囲気や挨拶について
- 新着コメント2026.02.08
- 初診料算定後の疾患別リハビリテーションについて
- 新着コメント2026.02.07
- リハ室でのトイレ介助について
- 新着コメント2026.02.07
- 理学療法士ほ目指すにあたって
- 新着コメント2026.02.07
- リハビリテーションの施設基準(器械・器具)
- 新着コメント2026.02.05
- クリニック、訪問リハの退職金について
- 新着コメント2026.02.05
- 予防訪問リハビリ12ヶ月減算について
- 新着コメント2026.02.04
- 老健リハビリの加算について
- 新着コメント2026.02.04
- リハ施行時の感染対策について
- 新着コメント2026.02.04
- 転院時のリハビリテーション総合実施計画書の同月算定について
- 新着コメント2026.02.04
- セラピストの副業や単発バイトについて
- 新着コメント2026.02.02
- 認定理学療法士について
- 新着コメント2026.02.02
- 診療報酬改訂後のがん患者リハビリテーションでの退院時リハビリテーション指導料算定
- 新着コメント2026.01.30
- 県士会って継続するべきですか?
- 新着コメント2026.01.28
- クリニックの就業規則について
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。