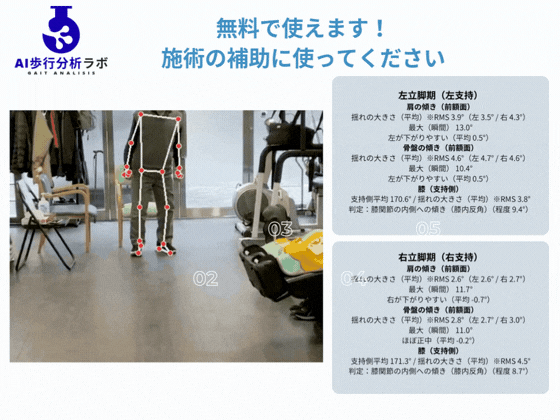理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
PT-OT-ST.NET
PT-OT-ST.NET掲示板
掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:3919 2024年12月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
- 関連タグ
- 疑義解釈
権限がありません
修正履歴
- 2024.12.04 12:54
-
2:チャピ子更新日:2024年12月05日 23時01分
白本(診療報酬点数表改正点の解説)上では、
該当の職種が
6分間で歩行できた距離と酸素飽和度(+脈拍)を
カルテに記載し、医師が診断(確認)したもの
と解釈できます。
ザックリと言ったら、「6分間に歩いた距離とSpO2がどれくらい下がったか?」が記載されていれば最低限通ってしまうのが現状です。
必ずしも「6分間歩行試験」に則ってはいないのが現状かと思われます。
医師でも廊下で他患が歩いている横で周囲の人たちのペースに合わせた歩行で「6分間歩行もどき」をやっている方々も居るのが現状ですよ…
6分間歩行の方法としては、可能な限り「呼吸リハビリテーションマニュアル」に則った内容が望ましいとは思います。
私個人としては、トレットミルでは何らかの定量負荷(抵抗)がかけられてしまっている段階で「運動負荷試験」に近しいものと解釈してしまいます。
ちなみに場所の問題でなく、研究的な視点からの短距離での考察は、PT学会などで「単一施設レベルでの健常人モデル例」は散見されます。あくまで「健常人のみ」ということをご考慮いただいた上でご参考に。
または有料登録制になってしまいますが、『D211-4 シャトルウォーキングテスト』も考えられてもよろしいかと。シャトルウォーキングテストであれば10m(+α)の歩行路と、CD音源を再生できるプレイヤーがあれば実施できます。施設単位か個人単位で登録すれば学会発表でも使用できます。こちらもご参考に。
当院では、6分間歩行試験の依頼があった際には使用していない病棟の廊下(すぐ隣に使用している病床があり必ず人手がある場所)で30mラインに目印を置いて実施しています。 -
1:PTPTPT更新日:2024年12月04日 22時19分
個人的にはトレッドミルを利用するのもいいと思いますが、いくつか懸念があります。
①スピード調整はどうするのか?
試験自体は自由歩行になるため被検者の歩行速度に応じて、検者が適宜スピード調整できるかが課題と思います。被検者の年齢や体力に寄りますが、検者がスピード調整が上手く出来ないと6分間歩行試験のコンセプトである「出来るだけ長い距離を歩くこと」が達成できなくなる恐れがあります。
②平坦な環境を確保できるのか?
本来は平坦な場所での歩行になるため、トレッドミル自体に傾斜がないことが必要です。
③休憩はどうするのか?
試験中は何回でも休憩して構わないことになっていますが、その度に検者による機器操作が必要と思います。また、休憩後に再度、歩き始める際の機器操作を含めるとタイムラグが生じて、①と同様に6分間歩行試験のコンセプトである「出来るだけ長い距離を歩くこと」が達成できなくなる恐れがあります。
④歩行補助具はどうするのか?
試験中は歩行補助具を使用できますが、トレッドミルの大きさによっては使用し辛い場合があります。また、本来フリー歩行や杖歩行している人がトレッドミルの手すりを使用するのも避ける必要があります。
当院の取り組みとして、入院患者の場合は病棟廊下またはリハビリ室を周回してもらい、外来患者の場合はリハビリ室を周回してもらっています。周回する場合は小回りと遠回りで距離が異なるため統一するように注意しています。もし、周回するにしても直線が短い場合はカーブするたびに歩行速度が落ちてしまう場合があり、結果として歩行距離が伸びなくなるため要検討だと思います。直線20mあれば妥協かなと思います。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:時間内歩行試験について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:時間内歩行試験について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
- コメント待ち2026.02.24
- 個別サービス計画書について
- コメント待ち2026.02.24
- 感染症予防及びまん延防止のための対策について
- コメント待ち2026.02.18
- 回復期リハビリテーション入院料3
- コメント待ち2026.02.18
- 手術などの場合の早期リハビリテーション加算について
- コメント待ち2026.02.16
- 回復期病棟の早出、遅出のリハビリ単位について
- コメント待ち2026.02.12
- リハビリテーションデータ提出加算について
- コメント待ち2026.02.04
- 老健入所における加算の算定要件について
- コメント待ち2026.01.22
- 一体的サービス提供加算での口腔機能向上サービスのLIFE入力について
- コメント待ち2026.01.20
- 医療 訪問リハビリ期限について
- コメント待ち2026.01.15
- 精神での訪問リハビリについて
- コメント待ち2026.01.14
- 音声障害の算定について
- コメント待ち2026.01.13
- 訪問、通所、疾患別リハのリハビリ指示書の様式統一について
- コメント待ち2026.01.02
- クーリーフ治療の評価項目について
- コメント待ち2025.12.30
- 地域包括ケア病棟のリハビリ中止について
- コメント待ち2025.12.24
- 側湾症を学ぶために有効な参考書
- コメント待ち2025.12.23
- 電子カルテの生成AIについて(SSI)
- コメント待ち2025.12.22
- LIFEの実地指導開始について
- コメント待ち2025.12.04
- 地域包括ケア病棟のリハビリ1日2単位以上に、心リハ「集団療法」も含めてよいか?
- コメント待ち2025.11.21
- 【相談】発達ピラミッドの活用方法と手指の発達段階について教えてください
- コメント待ち2025.10.30
- 必要書類について
新着コメント
- 新着コメント2026.02.25
- リハの値段
- 新着コメント2026.02.25
- 副業について
- 新着コメント2026.02.25
- 「P84 専門性を生かした指導などのさらなる推進」の解釈について
- 新着コメント2026.02.25
- 興味関心チェックシート
- 新着コメント2026.02.24
- 休日リハビリテーション加算の算定方法について
- 新着コメント2026.02.24
- リハビリ以外の業務が20分につき1単位に含まれるのか?
- 新着コメント2026.02.24
- 回復期での実施計画書について
- 新着コメント2026.02.24
- 国の補正予算による賃上げについて
- 新着コメント2026.02.24
- 短期集中リハビリテーション加算と認知症短期集中リハビリテーション加算同時算定は可能?
- 新着コメント2026.02.22
- ペースメーカーの患者様の肩の痛み
- 新着コメント2026.02.20
- みなし単位
- 新着コメント2026.02.20
- 令和8年度診療報酬改定における、疾患別リハの新設項目「注7(離床を伴わない場合の減算および単位制限)」の解釈について
- 新着コメント2026.02.19
- 回復期リハビリテーション病棟変更内容
- 新着コメント2026.02.19
- 予防訪問リハビリ減算とマネジメント加算について
- 新着コメント2026.02.19
- セラピストのアクセサリー類の着用について
- 新着コメント2026.02.18
- FIM評価期間について
- 新着コメント2026.02.18
- リハビリテーション総合実施計画評価料算定要件について
- 新着コメント2026.02.18
- 休日リハビリテーション加算について
- 新着コメント2026.02.16
- 訪問リハ自費について
- 新着コメント2026.02.15
- 身体拘束、高齢者虐待防止の研修について
- 新着コメント2026.02.15
- リハビリテーション料
- 新着コメント2026.02.14
- マネージメント加算の会議について
- 新着コメント2026.02.14
- PTさんを目指し進路に悩む学生です
- 新着コメント2026.02.12
- 職場の雰囲気や挨拶について
- 新着コメント2026.02.08
- 初診料算定後の疾患別リハビリテーションについて
- 新着コメント2026.02.07
- リハ室でのトイレ介助について
- 新着コメント2026.02.07
- 理学療法士ほ目指すにあたって
- 新着コメント2026.02.07
- リハビリテーションの施設基準(器械・器具)
- 新着コメント2026.02.05
- クリニック、訪問リハの退職金について
- 新着コメント2026.02.05
- 予防訪問リハビリ12ヶ月減算について
- 新着コメント2026.02.04
- 老健リハビリの加算について
- 新着コメント2026.02.04
- リハ施行時の感染対策について
- 新着コメント2026.02.04
- 転院時のリハビリテーション総合実施計画書の同月算定について
- 新着コメント2026.02.04
- セラピストの副業や単発バイトについて
- 新着コメント2026.02.02
- 認定理学療法士について
- 新着コメント2026.02.02
- 診療報酬改訂後のがん患者リハビリテーションでの退院時リハビリテーション指導料算定
- 新着コメント2026.01.30
- 県士会って継続するべきですか?
- 新着コメント2026.01.28
- クリニックの就業規則について
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。