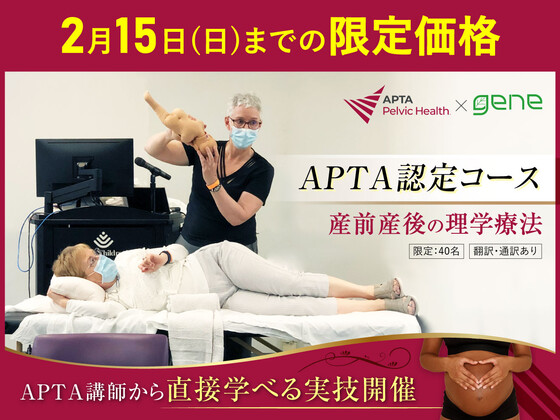理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
PT-OT-ST.NET
PT-OT-ST.NET掲示板
閲覧数:9616 2025年07月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
- 関連タグ
- リハビリ単位数
権限がありません
修正履歴
- 2025.07.18 00:46
- 本文を修正しました
- 2025.07.18 00:32
- 本文を修正しました
- 2025.07.18 00:22
-
10:ス更新日:2026年01月06日 12時41分
え?僕の職場は1日10単位取らなくても文句を言う人はいません。経営面から考えると18単位は取って欲しいところでしょうけど、カルテ記入、カンファレンス、実動との適合性を考慮すると15.16単位が適正と思います
-
9:通りすがりの急性期セラピスト更新日:2026年01月04日 16時46分
18単位では無く、18単位相当ですよね。カンファレンスやその他の業務も単位数に含めてあると仮定しますと、月の平均単位数は16〜17単位ぐらいでは無いでしょうか?、優しい職場だと思います。
経営層からはもっと稼ぐように指示は出ている中で、リハビリの管理職の方は妥当なラインで調整されているのでは無いでしょうか?、おそらく見えていないだけで、業務改善の取り組みはなされていると思われます。働き方改革で定時で終わるようになってきていますし。
現場で働かれている方が文句ばかり言っても仕方がない訳で、厳しいですがその職場が嫌なら辞められていいのではないかと思います。他はもっと厳しいですよ、内容からして新人さんでは無さそうですが、まだ一つの職場でしか働かれていないのであれば他を知ることも必要です。
給料を貰っている以上、労働としての対価を返さないといけない訳ですから、もっと視座を上げて働いた方が患者さんのためになるし自分自身のためにもなるかと思います。
あくまでも一意見ですが、求められている患者さんに関わる時間は遵守しつつ、付随する関連業務の効率化を図るために自分に何が出来るか、上司を納得させられるだけの改善案を上申して、業務の質を上げる方に目を向けて働かれた方が、もう一度お伝えしますが患者さんにとっても自分自身にとっても良いと思いながら自分は日々の業務に取り組んでいます。 -
8:通りすがり更新日:2026年01月01日 15時25分
8時間労働18単位ならむしろ優しい職場だな・・・と感じてしまいました。
-
7:にゃうー更新日:2025年08月30日 09時48分
平成20年頃から10数年、回復期で勤めてましたが、1人3単位×7人=21単位(7時間)、カルテ1人4分×7人=28分、患者間移動5分×6回=30分(広い病院ではない)でした。休憩は絶対取ってました
これで全て脳血管疾患なら50,000円程度、運動器なら38,000円程度になります。もちろん毎日21単位ではありません。リハ中止や病床数の増減もありますので。
さて、みなさんお給料はいくら欲しいですか?(法に則った提供をするのは大前提)
ここを意識しないで何単位が適正か?と考えても意味無いですし、上層部・経営陣には絶対響きません。 -
6:mr.T更新日:2025年08月19日 15時49分
4,5の方がおっしゃっているのはローカルルールではなく病院独自のルールですね.
私も無床外来ですが,無床外来の場合はリハ前診察時間を考えると1患者あたり30分を見ているので30分×1単位が妥当なのではと思います.それでも遅刻があったり,検査治療が長引いたりで思うようにいきません.
急性期や入院の場合は,リハ前診察もなく複数単位もとれるので無床外来よりも増えるのではないかと思います.
ただ回復期に勤めていた時は,就業時間のうち1時間は書類のための時間となっていたので16単位くらいでした.
これも時代ですかね.昔よりホワイトでした.
急性期病院勤務時に監査で注意されたのは実施時間が20分ぴったり(20分が多い),実施患者間で間隔がない(PT,患者の移動時間等),高齢者での複数単位(連続で動けるだけの耐久性,休憩時間が必要),評価は実施時間に含まないです.あとは実施計画書の記載不備くらいでしょうか.
4の方でリハ実施時間中に途中まで記載して終わって完結させるも,電カルに入力途中の記載時間が残ってしまうと証拠となるのでアウトです.電子カルテは記載時間,修正時間が残るので実施時間の途中で記載して不正請求になった事案がありました.個人がやられていたのでおそらく内部告発でしょう.また介入中に計画書はアウトだと思います.自主トレーニングメニューの作成は患者さんと話しながら作れば全然問題ないのではないでしょうか?物療は実施時間に含まれないのでこれも全然OKだと思います.
パラパラさんのお話からすると20年以上前の話を聞いているようです.経営のことを考えると単位至上主義になりがちですが,気持ちよく働ける職場ではないですね. -
5:あんらっきー更新日:2025年08月13日 13時46分
急性期・地域包括ケア・回復期リハの各病棟のあるケアミックス病院の管理的な仕事をしています。私の勤務する施設では、目標値は17.5単位です。先月の実績値としては、管理部門担当者を含むリハビリ全体の平均取得単位数は15.5単位、管理部門を含まない場合は16.21単位、回復期の専従のみだと17.1単位でした。一日の勤務時間が7時間45分です。これは、早退・午後勤務の人間も1日出勤したとみなした平均値です。出していないので、はっきりとした数字ではないですが勤務時間当たりの平均にすると、もう0.5単位程度は上がると思います。
外来・急性期病棟の場合は、一人当たり3単位実施して一日6人という事もできず、記述に時間がかかるので、少し効率が悪いですね・・・。
当院でいうと、訓練中に診療記録は書きませんが、カルテ内に訓練中の様子のメモ(という言い方の診療記録ですが・・・)は記載しています。emilioさんと同様のルール、患者さんのすぐ横で監視程度でできる自主練習中に限りですが・・・。
リハが終了してから、診療記録という形で最終的な記述修了という流れです。
診療記録を書き終えている訳でもないので、個人的には、違反だとも思いっていません。この辺りは、施設によってローカルルールとしていて、何処かの施設で同様の事を行っていて報酬返還などになったら、変えていく予定です。
定時に帰宅している職員も多いですが、残業しなければ終わらない人も多いです。要領が良い人が早く帰っている感じですが、診療録記述の為に、残業する人はいます。残業する人はある程度、決まっていて、上手くできない人は、要領の良い人にコツや運用などを聞かない方が多いです。早く帰れというのは、基本的には言いません。今の仕事がどのぐらいに終わるのか?を聞いて回る事は、時々あります。
仕事がどうしても終わらない人は、回復期の専従に配置転換してもらい、一日に6人を訓練・記述する業務についていただいています。それでも業務時間内には終わらない様子ですが・・・。
管理部門の私としては、18単位近くは取得しておく方が、後々退職後の職員の補充が継続的に実施されるためにも良いかと思います。
という訳で、私の勤務する職場の目標単位数は17.5単位が目標となっています。 -
4:emilio更新日:2025年08月13日 08時54分
前職の病院のローカルルールでしたが、介入中の計画書作成・自主トレーニングメニューの作成はOKになっていましたね。自主トレーニングをしていただいている・物理療法中・エルゴメーター実施中等、何かしらのことを行っていて、かつ自身の手が空く場合に、患者のすぐ横で見守りながら、という条件付きですが。
カルテ記載はどうしても終了まで何があるかわからないので、電子カルテなら途中まで記載して(訓練メニューや、患者の主訴等を忘れないうちに書き込んでおく等)、後ほど修正して完結させるスタッフもいました。
ただし、「介入中の患者に限る」ですが。
その病院の責任者のスタンスとしては「その患者の計画書等の作成なら、その患者に関する業務を行っている。マンツーマンで当該患者の業務を行っているのだから、介入時間に含めてはならない理由がない」とのことでしたね。個人的には賛同していました。が、当然そんなことはどこにも根拠が書いていません。
故のローカルルールですね。
パラパラ様の勤務先では何かローカルルールのようなものはあるのでしょうか。
よほど施設基準や算定根拠に逸脱した内容でなければ、ある程度ローカルルールが設定されていることが多いのではないかと思いますが…
単位数のことを忘れていました…
急性期病棟で内科・脳神経外科中心のチームが16~17単位、整形外科中心のチームが18単位、回復期が19~20単位が目標でした。 -
3:くろちゃん2更新日:2025年07月21日 11時27分
当方、現在老健の管理職を行っています。
以前は法人内の回復期にも一般職として在籍しており、参考になればと思い書き込みさせていただきます。
当方回復期では、助手さんが在籍し、リハ室と病室の送り迎えは助手さんが実施。1回の介入は基本2単位、1単位や3単位の方と組み合わせ、7~9名の患者様を毎日担当し、18単位以上実施していました。
カルテは介入後に実施し、実施した分は実働で残業代を頂いていましたね。
介入はきっちり20分.40分.60分で終了するようにコントロールする能力が求められましたが、助手さんが移動と物理療法の時間を受け持ってくれるため、徒手介入→物療の順番で実施することで時間コントロールはしやすかった覚えがあります。
また、カルテ記載や計画書など各種書類関係の作成も、電カル上の設定やフォーマットの工夫で簡潔化を図り、記録時間の短縮をチームとして成功させたことで、残業時間の削減に成功しました。確か、平均20時間程度の残業が10時間未満になって法人内で取り組みの表彰と標準化の仕事が舞い込みましたから。
文面から推測ですが、パラパラさんは20分きっかりでの介入終了が難しい環境にあるのではないでしょうか?
訓練中にカルテを打ち込んでいるセラピストは論外ですが、効率よく介入を実施するための工夫として、助手さんの導入や書類・カルテの記載方法の見直し等を提案してみるのはいかがでしょうか?
もちろん、経営的な視点は重要で、加算の算定ができない30分や45分で介入している場合には、パラパラさん自身も、20分.40分といった時間でプログラムが終わるよう見直しをするか、逆に内容を追加して40分、60分で単位が取得でいるようプログラム内容の追加をする必要もあると思いますが。 -
2:Mokona更新日:2025年07月18日 14時08分
整形外来で24単位診てます。正直、残業代も出ないのできついですね。
新患がいる場合は新患一人につき5~10分は欲しいですね。医師が適切な評価を行っていない関係で画像所見、red flag、病態評価、患部評価、全体評価etc..いわゆる診断的な評価を行わなければならず、これの記載も行うためカルテ記載時間は正直欲しいです。2回目以降は大きく記載内容に変化がないためそこまで時間は必要ありませんが・・。カルテ記載、始業前の清掃などを含めると18~20単位/日が妥当だとは思います。ただ、病棟の場合は他の忙しさもあると思うのでこれに限らないと思いますが・・。参考までに。
私の場合、病院には平均的に12時間程度拘束されますかね。ちなみに管理職ではありませんよ。
こういった業務量から鑑みると18~20単位が妥当かな、と思います。整形外科クリニックにため参考になるかはわかりませんが
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:1日の適正な単位数
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:1日の適正な単位数
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
- コメント待ち2026.01.25
- 加算算定について
- コメント待ち2026.01.22
- 疾患別、地域包括ケア病棟の専従:休診日日直(電話・カルテ出し)を「振替休日」にする運用ってアリですか?
- コメント待ち2026.01.22
- 一体的サービス提供加算での口腔機能向上サービスのLIFE入力について
- コメント待ち2026.01.20
- 医療 訪問リハビリ期限について
- コメント待ち2026.01.15
- 精神での訪問リハビリについて
- コメント待ち2026.01.14
- 音声障害の算定について
- コメント待ち2026.01.13
- 訪問、通所、疾患別リハのリハビリ指示書の様式統一について
- コメント待ち2026.01.02
- クーリーフ治療の評価項目について
- コメント待ち2025.12.30
- 地域包括ケア病棟のリハビリ中止について
- コメント待ち2025.12.24
- 側湾症を学ぶために有効な参考書
- コメント待ち2025.12.23
- 電子カルテの生成AIについて(SSI)
- コメント待ち2025.12.22
- LIFEの実地指導開始について
- コメント待ち2025.12.04
- 地域包括ケア病棟のリハビリ1日2単位以上に、心リハ「集団療法」も含めてよいか?
- コメント待ち2025.11.21
- 【相談】発達ピラミッドの活用方法と手指の発達段階について教えてください
- コメント待ち2025.10.30
- 必要書類について
- コメント待ち2025.10.20
- 歩行分析アプリ LocoStepもしくはAYUMI EYEの導入効果
- コメント待ち2025.10.28
- 病院内みなし事業所における、主治医と指示医間の情報提供について
- コメント待ち2025.10.10
- 認知機能検査の算定回数
- コメント待ち2025.10.04
- 入棟時のFIM説明について
- コメント待ち2025.10.03
- 訪問リハにおける医師の診療について.
新着コメント
- 新着コメント2026.01.29
- 実習生の担当症例に対する誓約書(同意書)について
- 新着コメント2026.01.29
- 転院時のリハビリテーション総合実施計画書の同月算定について
- 新着コメント2026.01.29
- 認定理学療法士について
- 新着コメント2026.01.29
- 上限越えリハの対象疾患
- 新着コメント2026.01.28
- クリニックの就業規則について
- 新着コメント2026.01.27
- 2026年度の運動器リハについて
- 新着コメント2026.01.27
- 20代後半から40代の貯金額
- 新着コメント2026.01.26
- 通所リハビリの短期集中個別リハビリ加算の算定要件について
- 新着コメント2026.01.26
- 2026年介護報酬改定について
- 新着コメント2026.01.24
- リハビリテーション総合実施計画書作成と評価料算定について
- 新着コメント2026.01.24
- 総合実施計画書様式23
- 新着コメント2026.01.24
- 医療保険の複数事業所介入
- 新着コメント2026.01.24
- 頻繁に求人を出している職場への転職
- 新着コメント2026.01.23
- 12ヶ月超の減算について
- 新着コメント2026.01.23
- 転職について
- 新着コメント2026.01.22
- 看護師向け講習
- 新着コメント2026.01.22
- 特養でのご利用者様に対する保湿ケアについて
- 新着コメント2026.01.21
- リハビリテーション実施計画書書式
- 新着コメント2026.01.21
- 急性増悪について
- 新着コメント2026.01.20
- 自立支援を利用した精神訪問看護と介護保険での訪問看護リハビリの併用可能か?
- 新着コメント2026.01.19
- 訪問看護Ⅰ-5
- 新着コメント2026.01.19
- リハビリテーション実施計画書の作成時期と交付タイミングについて
- 新着コメント2026.01.17
- 加算型老健での感染症対策と、県からの実地指導や監査について
- 新着コメント2026.01.16
- デイ 短期集中リハビリについて
- 新着コメント2026.01.09
- 訪問リハビリの指示に関して、回数を減らす場合
- 新着コメント2026.01.08
- 書類について
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。